中之島コース
天満天神繁昌亭をスタート地点として、中之島を西へむかいます。
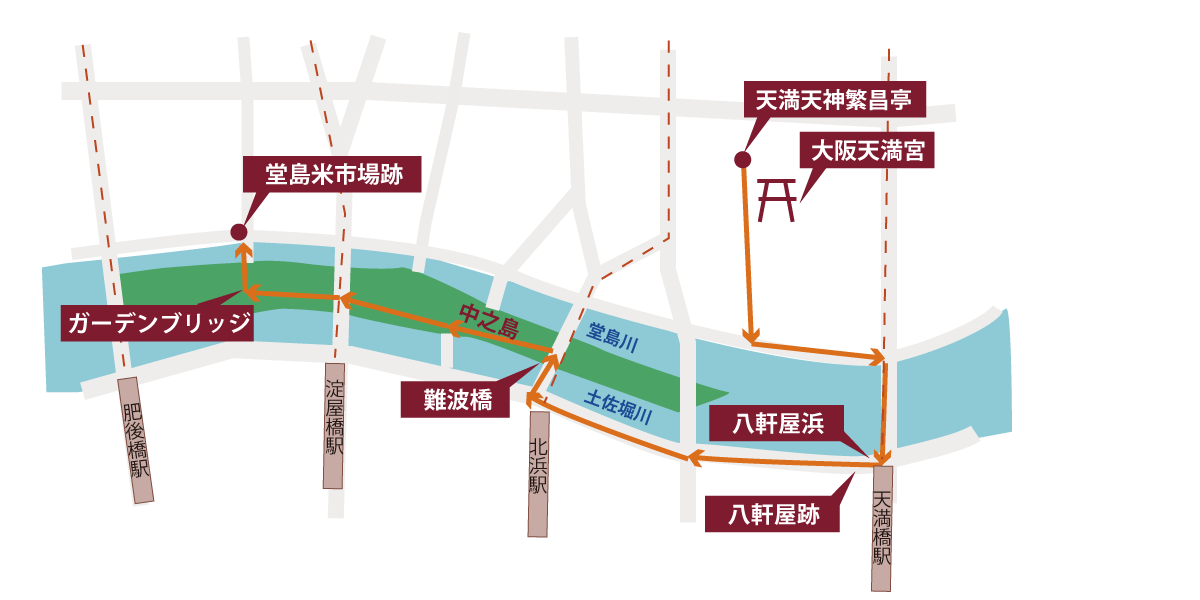
『初天神』
天神さまへお参りに出掛けようとする熊。その姿を見た息子の寅が、 一緒に連れて行ってくれとせがみます。あんまり騒ぐので、 仕方なく連れて行くことに。ところが寅、出掛ける前に何も買わないと約束したのに駄々をこね、 結局、露店で飴やダンゴを買ってもらいます。「やっぱり、寅なんかつれてこんだらよかった。」と熊、お参りを済ませ、 今度は親子で凧あげをすることになりました。どこまでも高くあがる凧に、 今度は父親の方が夢中に。その様子を見た寅は・・・「おとっつぁんなんかつれてこんだらよかった。」
天満天神繁昌亭から大阪天満宮へ
 天満天神繁昌亭は2006年オープンの寄席で、上方落語の中心地というところです。
そのすぐお隣が大阪天満宮です。
古典落語「初天神」の舞台です。「初天神」の“天神”とは、菅原道真公のこと。
その道真公が祀られている天満宮の新年最初のご縁日(1月25日)だから「初天神」というわけです。
7月の「天神祭り」はもちろんこちら天満宮のお祭りです。
天満天神繁昌亭は2006年オープンの寄席で、上方落語の中心地というところです。
そのすぐお隣が大阪天満宮です。
古典落語「初天神」の舞台です。「初天神」の“天神”とは、菅原道真公のこと。
その道真公が祀られている天満宮の新年最初のご縁日(1月25日)だから「初天神」というわけです。
7月の「天神祭り」はもちろんこちら天満宮のお祭りです。
噺の最後に凧あげの場面がありますが、江戸時代初期ぐらいまで凧のことを「イカのぼり」「イカ」と
呼んでいたそうで、元は大人の遊びで、凧によるケガ人や死者まで出るようになり、幕府より
「イカのぼり禁止令」がでるが、やめたくない町衆が「これの名前はタコです、
イカではありません」という言い訳をつけて、タコという名前に変わったといわれています。
その時に凧という漢字もできたようです。
『三十石』
お伊勢詣りの旅の最後に喜六と清八は京から大坂へ。三十石の夜船に乗ろうと伏見・寺田屋浜にやってきます。 船に乗り込むと、物売りのにぎやかな声が響き渡り、客同士もワイワイ騒いでいます。 夜更け、いよいよ船が動き出し、途中川に落ちるものがいたり、泥棒さわぎなどもありますが、 船頭の歌う舟歌とともに、のどかな雰囲気の船は、八軒家船着場へと向かいます――。
天満橋から八軒屋船着場を眺め、八軒屋跡の碑へ
 京・伏見から大坂・八軒家までの船の中のやりとりを描いた「三十石」。
三十石船とは、米を三十石積めることに由来しています。京から大坂(下り)は6時間、
川の流れに逆らう上りは倍の12時間。歩いたほうが早かったという話もありますが、夜寝ている間の移動は便利だったようです。
八軒家の名は八軒の船宿や飛脚屋が軒を並べていたことからそう呼ばれました。
京・伏見から大坂・八軒家までの船の中のやりとりを描いた「三十石」。
三十石船とは、米を三十石積めることに由来しています。京から大坂(下り)は6時間、
川の流れに逆らう上りは倍の12時間。歩いたほうが早かったという話もありますが、夜寝ている間の移動は便利だったようです。
八軒家の名は八軒の船宿や飛脚屋が軒を並べていたことからそう呼ばれました。
当時の船着場は、土佐堀通り沿いにある永田屋昆布本店の前に(写真右)八軒屋船着場跡の碑として残されています。
碑から近くのの高倉筋には当時の浜に繋がっていたであろう、階段が残されています。階段を上がりきると「熊野街道」の
碑が見えます。今の感覚では熊野(和歌山)ははるか先なのですが、昔はここ八軒屋が熊野を目指す基点となっていたようです。
『遊山船』
ある夏、花火見物のため難波橋に来た喜六と清八。 錨(いかり)模様の浴衣を着た賑やかな稽古屋連中を冷やかします。 清八が「さても綺麗な錨の模様!」と声をかけると、舟から「風が吹いても流れんように」と粋な返事。 感心した二人でしたが清八は「お前のかみさんにはとても言えんだろう」と言います。 そこで喜六は家に帰ると、押入れにあった汚れた錨模様の浴衣を女房に着せ、 舟のかわりに盥(たらい)の中に座らせ、天窓の上から浴衣のあまりの汚さに「さても汚い錨の模様!」、 すると女房がシャレをきかして「質に置いても流れんように」
土佐堀通りを北へ進み難波橋へ
 難波橋(なにわばし)は中之島公園を挟んで堂島川と土佐堀川に架かる橋。天神橋、天満橋とともに浪華三大橋と言われました。
江戸時代には200メートルを超える木製の反り橋で橋からの眺めがよかったそうです。何度か付け替えられ、大正期に当時としては
めずらしいライオン像が阿吽のライオンとして2体づつ置かれました。今の橋は1975年に修復完成されたようです。
難波橋(なにわばし)は中之島公園を挟んで堂島川と土佐堀川に架かる橋。天神橋、天満橋とともに浪華三大橋と言われました。
江戸時代には200メートルを超える木製の反り橋で橋からの眺めがよかったそうです。何度か付け替えられ、大正期に当時としては
めずらしいライオン像が阿吽のライオンとして2体づつ置かれました。今の橋は1975年に修復完成されたようです。
「三十石」もそうですが「遊山船」の主人公も喜六と清八、「お伊勢参り」や「野崎参り」もこの二人づれです。
上方落語登場ナンバーワンは喜六だそうです。噺によっては独身であったりする場合もあるようですが、「遊山船」
ではおかみさん(お咲さん)も登場します。同じ登場人物、同じ季節、おなじ場所で展開する「船弁慶」もおもしろいですね。
『米揚げ笊』
仕事もせずにブラブラしている男が、笊(いかき)売りを始めます。うちの笊は、後ろから叩いても壊れないことをウリにして 売っておいで、目の前で後ろから叩けばいい。 そう教えられ、大小の笊を担いで「米をあげる笊~」と声を張り上げ 歩いていたら、「こーめーをーあーげーるー」という言葉に ある米問屋の主人がほれ込み、 「米を揚げる」と聞けば祝儀が貰え、「笊を座敷に全部上げる」「兄弟は上に姉と兄がいるだけ」 と言えば祝儀が倍々になりました。姉様は「京都の上の屋敷の上の女中をしている」と聞けば 主人は更に興奮して、サイフごとくれてやる~!でも、そんなにたくさんの祝儀をくれていたんでは 店が崩れてしまいますと、番頭が主人に言ったところ、 男が「大丈夫です、うちの笊は後ろから叩いても崩れません」
ガーデンブリッジを渡り堂島米市場跡へ
 落語の中で堂島では手招きをすると手先が下がってしまうので、手のひらを上に向けて下からすくい上げるように
手招きする。それを「堂島のすくい呼び」と呼ばれていた。とあたかもそんな習慣があったかのように表現されていますが、そんな
呼び方はないらしく、いい加減に噓の名前をつけてしまうあたりが落語の面白さのひとつですね。
落語の中で堂島では手招きをすると手先が下がってしまうので、手のひらを上に向けて下からすくい上げるように
手招きする。それを「堂島のすくい呼び」と呼ばれていた。とあたかもそんな習慣があったかのように表現されていますが、そんな
呼び方はないらしく、いい加減に噓の名前をつけてしまうあたりが落語の面白さのひとつですね。
写真真ん中下の橋がガーデンブリッジです。堂島米市場跡のモニュメントは橋の北詰めにあるのですが、現状(2018年9月初旬)は写真右のように
ロープが張られ、解説の看板もない状態です。10月下旬に新しいモニュメントに変わるようで、どんなものになるのか楽しみです。
橋の上にも大阪の古い地図や浮世絵が飾られていますが、そういうものも含めて綺麗に変わるんでしょうか。