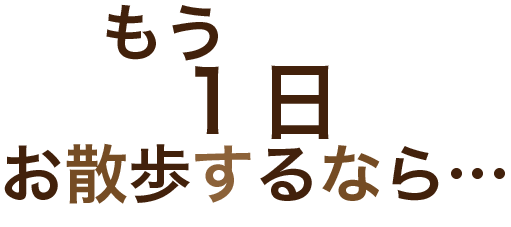さいたま市立博物館
お散歩して見つけた古墳の出土品が常設展示されています。
埴輪や勾玉などを見ることができます。
自由研究するなら、古墳と一緒に、博物館にある出土品も見てみましょう。
それから、この古墳のある地域に貝塚があったそうです。
古墳ができた時よりもさらに数百年から数千年前の遺跡です。
そんな昔からこの地域に人が住んでいたのですね。
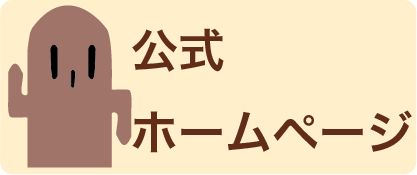
大宮氷川神社
先に紹介した、さいたま市立博物館は、大宮氷川神社の参道沿いにあります。
この参道を使えば迷うことなく大宮氷川神社にたどり着きます。
大宮氷川神社は神社の記録によると孝昭天皇(こうしょうてんのう)の頃と言われています。
孝昭天皇は第5代天皇ですから古事記や日本書記の世界の天皇で機械的に西暦何年に在位したとかいうことができません。
大宮氷川神社は、おそらく2000年くらい前には建立されていたのではないでしょうか?
ということはお散歩で見つけた古墳に埋葬されていた人たちも氷川神社に参拝したかもしれません。
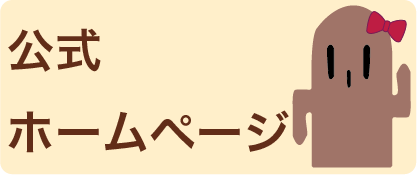
古墳のできた頃は何が起きていた?
お散歩で回った古墳は6世紀後半から7世紀にかけて作られたそうです。西暦でいうと550年とか650年とかでしょうか。
その頃世の中では何が起きていたでしょう?
- 538年 仏教伝来
- 538年 仏教伝来
- 593年 聖徳太子 推古天皇の摂政になる
- 607年? 奈良法隆寺の創建
- 645年? 大化の改新
- 708年 平城京(奈良の都)遷都
その他の埼玉県の古墳を見たいときは?
さきたま古墳公園(埼玉県行田市)
さきたま史跡の博物館では、古墳からの出土品を多数見学することができます。
公園内にある「稲荷山古墳」から1968年に出土した全長73.5センチメートルの「金錯銘鉄剣(きんさくめいてっけん、きんしゃくめいてつけん)」です。
他の出土品とともに1983年に国宝に指定されました。
この剣には文字が刻まれていて、そこに「獲加多支鹵大王」(ワカタケルノオオキミ)とあります。
「獲加多支鹵大王」とは、雄略天皇(21代天皇)のことです。
推古天皇(33代天皇・聖徳太子の母親)より前の天皇の存在は歴史資料的にはよくわからないのですが、この剣に刻まれた文字が雄略天皇が実在した証拠の一つに数えられています。

もっと調べたい時は?
このホームページで紹介した古墳は「側ヶ谷戸古墳群(そばがいとこふんぐん)」と呼ばれる古墳群です。
埼玉県指定重要遺跡となっています。この古墳群の近くに次のような古墳群があります。
合わせて調べてみてはいかがでしょう。
- ※ウィキペディアにリンクします。
- 大久保古墳群(おおくぼこふんぐん)
- 植水古墳群(うえみずこふんぐん)
- 土合古墳群(つちあいこふんぐん)